 |
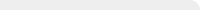


|
 |
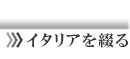 |
| 第15回 イタリアからきた“年賀状” |
☆
|
12月が超繁忙月である小売店でありながら、12月31日決算という日本では稀な事業年度制を『イタリア自動車雑貨店』は採っている。これはたぶんに僕の性格的な問題によるもので、会社年度の始めと終わりが、暦上のそれと一致しているという明快さを理屈抜きに好むからである。
しかし、そのおかげで、年末から年始にかけては時間の流れを的確に捉えられないような感覚に、ここで仕事をしているとずっとつきまとわれることになる。特に去年は年末ギリギリまでイタリアやドイツから荷物が飛び込んできて、それの入荷処理をして店頭に並べ、さらにはホームページにアップ、そして棚卸、新年度への在庫表の更新と、処理しなければならないことが間断なく続いた。
そのなかでも大晦日は営業を続けながら今年1年の締めをして、さらに翌日からの新年度の準備を完了しなければならないわけで、慌しさもピークになる。20世紀最後の12月31日は、ドタバタドタバタ、そうやって暮れていった。 |
☆☆
|
一瞬、腕時計に目をやると、針は午前0時を回っていて、21世紀はストンとやってきていた。20世紀を約半分生きた僕としては、ちょっとは感慨とやらにも浸りたかったけれど、迫るようにやってくる現実の仕事が、そんなものは追い払ってしまう。
あと何時間かしたら、いつものように店の扉を開ける。淡々と継続されてゆく日常。2001年1月1日、21世紀最初の営業日であるその日のその時間も、時計の針の進行以上のどんな意味も持たず、いつのまにかそこにいるのだろう。
メールをチェックしたら、ちょうど日本の新年の時間に合わせて、イタリアから“年賀状”が届いていた。Happy New Year!
2001の大きなタイトルの中で、2001がヘビのようにのたくっていて、最後にFrom Roberto, Lorenzo,
Christina, Angelica, Angela, Katia, Aldo, Martino(Dog) and all
your friends of Torino. と記されていた。
おそらくこれを送ってくれたのは、イタリア人の知り合いの中でもいちばん“IT”化の進んだLorenzoさんに違いないけれど、彼は家にコンピュータは持っていないので、きっと仕事場から送ったのだ。12月31日の午後6時(日本時間1月1日午前2時)に、イタリア人の彼が仕事をしているのか。
僕はすぐに電話をかけてみた。
プロント、と不機嫌そうな声で、いきなりLorenzoさんが電話にでた。楽しいメールありがとう、と言うと、すぐに彼は僕だとわかり、それから何度も、気に入ったか、気に入ったか、と訊いてきた。気に入ったよ、もちろん。
去年の11月に会ったときに、僕は日本の干支について彼に話し、来年がヘビの年だということを教えたりした。そのときは聞いているんだかいないんだか、なんかふにゃふにゃした感じだったけれど、彼はちゃんと覚えていたんだ。
こんな日に仕事?と訊くと、Lorenzoさんはそれには答えず、こんな時間に何をしてるんだ?と逆に質問を返してきた。仕事だよ、と答えながら、僕は地下1階にある彼の仕事場を思い浮かべていた。幅250cmくらいの大きな机、その上にコンピュータが3台、そして愛用のモトローラ社製の携帯電話、パテックの腕時計、ゴルフ雑誌。そういうものが雑然と置かれているのではなく、常に整理された状態でそこにある。几帳面
な彼の性格そのままだった。
やることが山のようにあって、と言ってから、なんだかそのあとの言葉が続かなかった。僕は彼にとってはちょっと早い新年の挨拶をすると、2月に行くよ、と言って電話を切った。 |
☆☆☆
|
イタリアに通い始めて間もなく、仕事を通して知り合ったLorenzoさんは、僕の知るイタリア人の中でも最も無愛想な一人だった。そんなこともあって僕はなかなか彼には馴染めなかったし、彼自身にもはるか彼方からやって来る東洋人の僕と、仕事を超えた親交を結ぶ気などなかったのだろう。会っている回数はそれなりなのに、彼と僕の間にはいつまでも衝立一枚が存在しているような感じだった。
あれは何という街だったのだろうか。4年近く前の春の夜、トリノ郊外の坂の多い小さな街の、柔らかな白熱灯の光が拡がるリストランテに僕らはいた。テーブルをはさんだ向かい側にLorenzoさん、そしてその隣には結婚間もない彼の妻、Mognaさん。快活で早口で身振り手振りの大きな、そしてとっても愛くるしいMognaさんの存在が、その場の雰囲気をとても和やかなものにしてくれた。
結婚した、ということを僕はLorenzoさんから直接ではなく人づてに聞いて知っていた。結婚オメデトウ、と彼の仕事場ですれ違いざまに声をかけると、35歳をすぎてようやく独身生活にピリオドを打った彼は僕の肩に手を置いて、次の日曜日に妻のMognaの実家に行くから一緒に来ないか、と誘ってくれた。それはそれまでの彼との関係からすると考えられない出来事だった。あの無愛想でちょっと冷淡そうな彼が僕を誘ったのだから。
そうして僕はトリノの中心部から50kmほど離れたMognaさんの実家に連れていかれた。行ってみて驚いたことに、彼女の実家というのは実は広大なワイナリーで、いわゆるお城のような家がバーンと目の前に現れてきたのだ。部屋数は20以上。あそこまでがうちのブドウ畑よ、とMognaさんが指差す「あそこ」は、はるか彼方で僕には判然としなかった。
午後には100人くらいの人を招いて、なんのパーティーだかよくわからない盛大なパーティーが催され、中庭では何故かファッション・ショーのようなものが行われていた。Mognaさんは招待客の間を縫うように歩き回って笑顔をふりまき、ガーデンテーブルでタバコをプカプカやっている僕のもとに時折やってきては、退屈ではないか、と気にかけてくれた。あの時、Lorenzoさんは一体どこにいたのだろうか。それがどうしても思い出せない。
ここで夕食じゃ知らない人ばかりで疲れちゃうでしょ。Mognaさんが僕の左腕に手をかけて言った。ここから少し離れた街によく行くリストランテがあるから、夜は3人でそこに行きましょ。
その夜、僕は初めてLorenzoさんと個人的な時間を共有することになった。彼はMognaさんに話しかける時でも、すべて英語を使った。彼女も英語で応えた。ふたりがイタリア語で話をすれば、その内容を理解できない僕が疎外されると思ってくれたのだろう。ふたりのそういう心遣いが嬉しかった。
Mognaさんはふたりの馴れ初め、家庭生活、そして何よりもLorenzoさん自身のことをたくさん話した。ちょっと内気で、人見知りで、誤解されやすく、でも私にはいつでも優しくて、結婚前も今も毎日2回は電話をくれると。
Lorenzoさんは、はにかんだように笑いながらそれを聞いていた。坂道の途中にある小さなリストランテでの、思い出に残る夕食だった。 |
☆☆☆☆
|
ふたりが離婚を前提にした別居生活に入ったのを知ったのは、去年の9月だった。これも僕はLorenzoさんから直接ではなく人づてに聞いて知った。イタリアではいわゆる冷却期間の意味なのか、離婚を申請してから3年経過して、その気持に変化がないことを確認されてはじめて正式にそれが受理される。
そのことを知った日の午後、僕はなんだか釈然としない思いを胸に、ポケットに両手を突っ込んで、彼の整然としたデスクに向かって階段を下りていった。
やあ、Lorenzoさん。新しい携帯電話が目に入った。Lorenzoさん、携帯電話、替えたの? デスクの上にはそれまでのモトローラのSTAR-TACではなく、V3688という機種が置かれていた。
ああ、と言って、それからニヤリと彼は笑った。僕は自分の新しいERICCSONをポケットから取り出してみせた。またニヤリと彼が笑い、ERICCSONを手にとってあちこち触り始めた。しばらくふたりで携帯電話の話をした。そのあいだじゅう、僕はLorenzoさんの表情だけを見ていたような気がするけれど、でも、それだけだった。結局、ほかのことは何も話さなかった。
もう、あと少しで夜も明けるという時間になって、大晦日の仕事に区切りをつけた僕は、パンダに乗って家に向かっていた。楽しかったことをたくさん思い出すことができた。Lorenzoさん、Mognaさんとゴルフに行って大騒ぎしたこと、寒風吹きすさぶ2月のトリノの極寒の夜に、僕の友人を交え4人で震えながら食事に行ったこと、街で偶然出会ったMognaさんがいきなり抱きついてきて面
食らったこと…。ファリナータというピザにちょっと似た、でもピザよりずっと安価な、それでいて抜群に美味しいそれを教えてくれたのもLorenzoさんとMognaさんだった。
今になってみると、とても複雑な気持になる話だけれど、去年の春先にはふたりに子供が生まれたという知らせも受け取った。女の子で、名前はVittoria。僕はキティちゃんのなんだかよくわからないマスコットのようなものをお祝いに送った。
5月にイタリアに行った時に、Lorenzoさんは僕にVittoriaの写 真を見せてくれた。目がクリクリしていて、どちらかというとMognaさん似の可愛い赤ちゃんだった。
ふたりが何故別れることになったのか、それを僕は知らない。ただ、MognaさんとVittoriaのことを何一つ尋ねなくなった僕の不自然さを、Lorenzoさんも気づいているはずだ。電話でも、会っていても、話題につまることがある。
おそらく、いつの日か、Lorenzoさんがそれを僕にポロっと話すことがあるような気がするけれど、いや、いや、もしかしたら、暮れの12月31日に、たった一人の仕事場から、そこにMognaとVittoriaの名のない“年賀状”を送ったことが、そのサインだったのかもしれない。
そんなことを考えながら、僕はクリスマスから新年にかけての美しいトリノの夜景を、爆音を発して走る改造パンダの中で思い浮かべた。その賑わう街なかに、一人暮らしには広すぎる4部屋もあるアパートに急ぎ足で向うLorenzoさんがいる。寂しいだろうな、と思った。 |
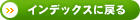
|
 |